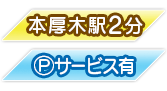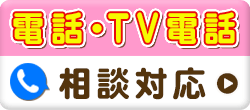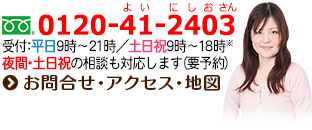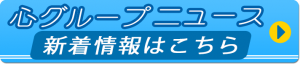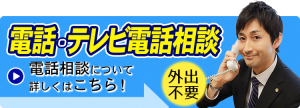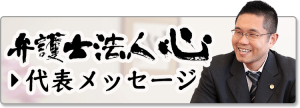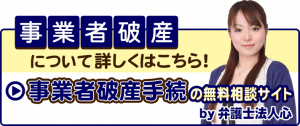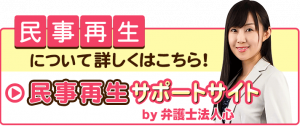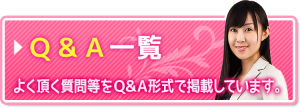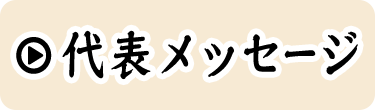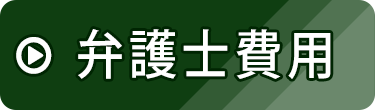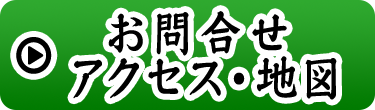会社更生法とは|条件・メリット等をわかりやすく解説
会社の経営状態が悪化した際、会社更生法を適用すすることで、会社を存続し続けながらも債務を整理することが可能です。
しかし、会社更生はとても複雑な手続きのため、弁護士のサポートが必要不可欠であると考えられます。
今回は、会社更生法についてわかりやすく解説します。
1 会社更生法とは?
⑴ 会社更生と会社更生法
会社更生とは、経営状態が悪化した会社が事業を続けながら債務を整理する方法です。
債務を整理することで経営を立て直すことができます。
会社更生法は、この会社再生の手続きを定めた法律です。
会社更生を行うためには、裁判所での手続きを経て、裁判所から更生計画を認めてもらう必要があります。
会社更生は倒産手続きの中でも、再建型・管理型の手続きと呼ばれています。
再建型とは財産も事業も維持しながら経営を続けること、管理型とは管財人が経営と財産を管理することを指します。
つまり、会社更生法を適用すると会社を消滅させずに済みますが、経営権は更生管財人に移ります。
会社更生法の適用を受けるには更生管財人の選任が必須ですが、更生管財人がつくことにより、会社の経営を良い方向に立て直すことができると考えられます。
また、会社更生法を適用したことで代表取締役はすることになりますが、更生管財人は今の経営陣の中から選任することができますので、今の経営陣が会社経営に引き続き関わることができる可能性もあります。
更生管財人には、経営陣だけでなくスポンサーや弁護士など、複数選任されるのが一般的です。
⑵ 会社更生法の適用条件
会社更生はどの会社でもできるというわけではありません。
条件を満たさない場合もあれば、適用が適切といえない場合もあります。
会社更生法の適用条件としては、以下のものが挙げられます。
・株式会社である
・開始決定要件を充たす
・資金が豊富にある
・営業キャッシュフローが黒字である
まず、会社更生法の適用を受けることができるのは株式会社のみです。
個人事業を営んでいる方やその他の種類の会社(合名、合資、合同)は利用できません。
また、開始決定要件を充たす必要もあります。
具体的には、①破産手続きの原因となる事実(支払い不能と債務釣果)が生じる恐れがある、または②債務返済を続けると事業継続に著しい支障をきたす恐れ(支払い不能に陥る可能性)がある、のどちらかを指します。
会社更生法手続きにはお金がかかります。場合によっては数千万円もの費用がかかることがあるため、中小企業よりも規模の大きい株式会社を想定しているとお考えください。
現在返済が苦しい状況にあったとしても、営業キャッシュフローが黒字であれば将来的な再建を見込むことができます。
しかし、本業の収支が厳しい状況である場合には債務を減らしてもいずれ倒産してしまいます。
将来性や社会的価値のある会社であり、利益を生み出せる会社でないと、更生計画は認められません。
⑶ 会社更生法の適用後の効果
会社更生法を適用すると、更生手続開始決定後と更生計画の認可後に以下のような効果があります。
まず、更生手続開始決定後は、①債務の返済禁止、②債権者による強制執行・担保権実行のストップ、③税金の支払い・滞納処分の制限、④経営権・財産管理権の管財人への委譲という効果があります。
また、更生計画の認可後は、①返済計画に沿った債務の減免効果と原則15年の支払猶予、②株式の取得・新株発行や社債の発行、会社分割などの組織再編など、更生計画に定めたことが実行されます。
【会社更生法を利用すると給与・退職金はどうなるのか】
会社更生法が適用され債務が減免されても、給与や退職金は共益債権となるため優先的に支払いが保証されます。
具体的には、給与は更生手続き開始前の6ヶ月分、未払い退職金も更生手続き開始前の6ヶ月分の給与に相当する額と退職金の1/3のいずれかの多い額が保証されます。
また、更生手続き開始決定後の給与も共益債権となり通常通り支払われますが、会社の財産状況によっては将来の賃金がカットされたりする可能性はあります。
会社更生法の適用により未払いの賃金・退職金が発生した場合には、労働者健康安全機構が一定の範囲で立替払いしてくれる制度(未払賃金建替制度)もあります。
2 破産・民事再生との違い
一般的に「倒産」という言葉は、業績不振の影響で事業継続ができない状態を指します。
法律上の「倒産」には、破産、特別清算、民事再生法、会社更生法の4つがあり、それぞれできることや適用範囲、手続きが異なります。
破産は、抱えている債務の全てを免除する代わりに、会社の資産を債権者に平等に分配する手続きです。
会社更生法と最も異なるのは、会社が消滅するという点です。
会社更生とよく比較される方法は民事再生です。
これらは共通している点も多くありますが、主に以下の点で異なります。
【民事再生の場合】
・個人や株式会社以外の会社にも適用できる
・管財人が選任されない
・経営権、財産管理権を維持する
・担保権者が権利行使可能
・税金の滞納、支払いも自由にできる
・株主が手続きに参加できる
・債務の支払い猶予期間が短い(10年)
会社更生法は、経営陣につき新体制を築きたい場合や、担保付きの債務が多いという場合に向いている手続きです。
他にも、中小企業ではなく大企業向きの手続きという点で異なるといえます。
3 会社更生法を適用するメリット
会社更生法を適用するメリットは主に3つあります。
具体的には以下の通りです。
・会社の経営を継続できる
・資産を守り、担保に制限を設けることができる
・会社組織を一新できる
まず、会社を消滅させずに会社の経営を継続することができるという点が挙げられます。
資金繰りが難しくなってきた段階で「破産」という選択肢もありますが、まだまだ利益を生み出せる見込みがある場合は、事業を続けて再建を図ることも一案です。
会社更生法を適用することで、それが可能となります。
また、担保となった資産を守ることも可能です。
会社更生は民事再生とは異なり、担保権の行使をストップできるため、会社の不動産を残したいという場合に最適です。
担保となっている資産でも、そのまま利用を継続できます。
さらに、会社の経営体制を変更することも可能です。
これまで組織一新について思うように進まなかったという問題を抱えていた場合でも、会社更生法の適用により管財人が入ることで組織変更が容易になります。
会社の改革も進めやすくなるため、更生法の適用を機会に一気に再建へと進めていくことが可能となるのです。
4 会社更生手続きの流れ
会社更生は、認可までに1年ほどかかります。
具体的には、以下のような流れで手続きが進んでいきます。
1 会社更生手続きの開始申立てをする
2 保全管理人の選任
3 開始決定
4 更生管財人を選定、更生計画案を作成
5 関係人集会で決議
6 更生計画の認可決定
7 遂行〜終了
事前の裁判所との打ち合わせの後、会社更生手続きの開始を裁判所に申し立てます。
申立て後に裁判所は保全処分命令を出し、保全管理人を選任します。
保全管理人は会社の財産や債務を管理します。
保全管理人の調査をもとに、裁判所は会社更生手続き開始決定を出します。
開始決定後は、更生管財人を選任します。
管財人は関係人集会などを開き、調査をした後に更生計画案を作成します。
更生計画案には、債務の返済計画のほか、新たな事業計画、再建方法なども盛り込んだ内容が含まれ、最終的には裁判所に提出となります。
その後関係人集会によって決議され、可決された後に、裁判所から認可決定が出されます。
認可後は、更生計画案が効力を持ち、更生計画を実際に進めていくことになります。
計画に沿って債務の弁済が終了するとき、会社更生手続きも終了します。
5 会社更生手続きは弁護士に相談を
会社更生手続きは複雑な手続きであるため、弁護士への相談・依頼が必要不可欠であると考えられます。
会社更生手続きを熟知した法律事務所に依頼しましょう。
当法人は、多くの会社破産・企業再生を扱ってきました。
会社に倒産のリスクが出始めている場合は、お早めに当法人の弁護士にご相談ください。